
「遺言は必ず自分で書かなければいけない?」
「遺言を自宅で保管している間に紛失してしまったらどうしよう…」
「遺言の作成方式に不備がないか不安」
将来に備えて遺言を書いておこうと思い立ったのはいいけれど、いざ相続開始となったとき、自筆して自宅で保管しておいた遺言が適切に執行されるのか不安な方も多いでしょう。
多くの方がイメージする遺言といえば、TVドラマなどでよく見るような、自宅で保管された本人手書きの遺言書かもしれませんね。
実は遺言の方式は大きく分けて3つあり、必ずしも自筆したものを自宅保管しておく必要があるわけではないのです。
本記事では、遺言の方式の各特徴について、相続手続きの専門知識を持つ行政書士が、手続きのポイントをご説明します。
当事務所では、上田市をはじめとして長野県全域において、建設業許可申請、農地転用、遺言相続、会社設立などの各種手続に関し、書類の作成代行や作成代理および官公署への提出代理などを幅広く行っています。
ご相談や書類作成のみの場合は全国対応もしますのでお気軽にご連絡ください。
遺言の方式は大きく分けて3つ

遺言の方式と各特徴
民法上、遺言には大きく分けて以下のような3つの方式が定められています。
①自筆証書遺言
本人が自分でその全文、日付、氏名を書き、押印する必要があります。
②公正証書遺言
公証役場等で、本人の口述内容を公証人が公正証書に作成する形の遺言方式です。
③秘密証書遺言
遺言書を自身で封筒に入れて封印し、公証役場にて遺言の存在を認証してもらう方式です。
方式ごとに作成ルールがある
せっかく作成した遺言でも、各方式において定められている要件を満たしていなければ、無効となってしまう場合があります。
遺言が無効になってしまった場合、初めから遺言はなかったものとして、結果的に遺産分割協議を行う必要が出てきてしまいます。
例えば、自筆証書遺言の場合ですが、相続させたい不動産の登記情報の記載が曖昧だと、相続登記をすることができないため、遺産分割を行うことになるのです。
相続において、生前のご自身の意思がきちんと反映されるようにするためにも、遺言の各方式における要件やルールについては、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。
どの方式の遺言を選べばいいのか?
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった3つの方式のうち、一体どれを選べばよいのか、悩むところではあると思います。
ご自身が遺言の保管をどの程度しっかりしておきたいのか、また、公証人による認証まで受けておきたいのか、皆さんそれぞれにお考えがあるでしょうから、この方式が絶対に良いと一概には言えません。
以下では、各方式におけるメリットやデメリットをご説明しますので、どの方式を選択するかの参考にしてみてください。
自筆証書遺言
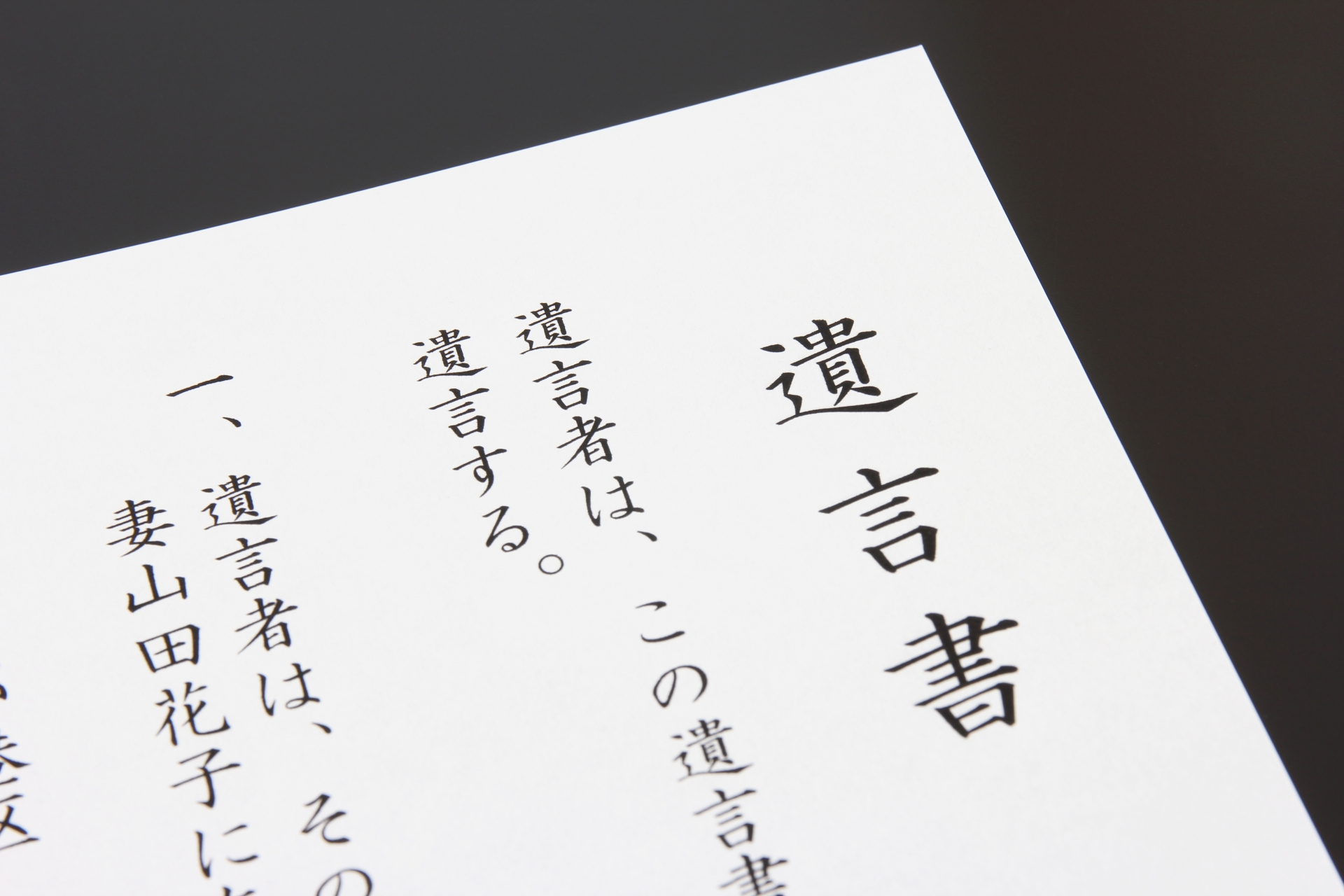
思い立ったらすぐ作成できるのがメリット
自筆証書遺言は紙とペンさえあれば、思い立ったときにいつでも作成することができるので、遺言書作成へのハードルが最も低い方式だと言えるでしょう。
公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、公証役場での手続きが必須となり、遺言の内容が決まっていても、準備期間に1ヶ月程度を要する場合があります。
すぐに遺言を残しておかないといけないような事情がおありだったり、手軽に遺言を書いておきたい気持ちがあったりする場合は、自筆証書遺言が一つの選択肢となってくるのではないでしょうか。
遺言の内容の不備に気づきにくくなってしまうという面も
比較的気軽に、そして迅速に作成できるのが自筆証書遺言の特徴ではありますが、一方でデメリットもあることを理解しておきましょう。
自筆証書遺言は、その名の通り自分で手書きをしなければならないという決まりがあります。
ご自身で作成が完結するので、第三者にチェックしてもらう機会がないまま遺言が完成することになり、万が一形式の要件を満たしていない場合に、その不備に気づきにくいというデメリットがあります。
先ほど述べたように、形式の要件を満たしていない遺言は無効となってしまう可能性があるのです。
自筆証書遺言の作成については、行政書士がサポートをさせていただくことも可能なので、不安や疑問がある場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
自筆証書遺言保管制度の利用も視野に
自筆証書遺言には、保管の際に紛失トラブルが起きないかという問題もあります。
一生懸命作成した遺言が、いざ相続となった段階で見つからないのでは困りますよね。
そういったトラブルを防止するために、自筆証書遺言保管制度の利用が可能となっています。
自筆証書遺言保管制度とは、法務局において、自筆証書遺言の原本と画像データを保管してもらうことのできる制度です。
この制度を利用するメリットとしては、遺言の紛失を防ぐことができるばかりではなく、法務局に遺言を預かってもらう際に、遺言作成の形式的ルールが守られているかを確認してもらえるということが挙げられます。
自筆証書遺言での遺言をお考えの方は、こちらの保管制度も検討されてみてはいかがでしょうか。
公正証書遺言
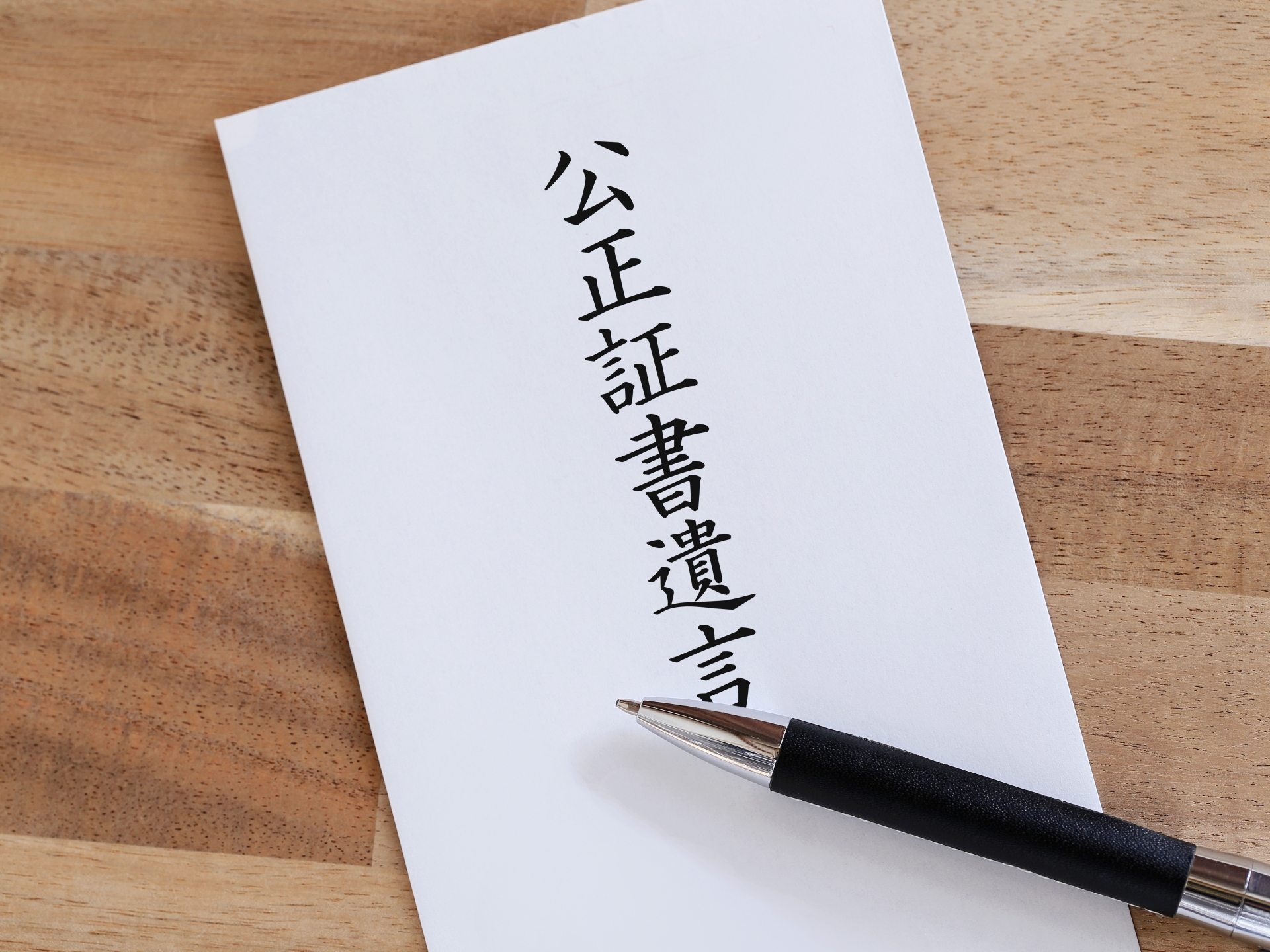
公証人が作成に立ち会ってくれるので安心
公正証書遺言とは、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が公正証書として遺言を作成してくれる方式です。
公証人が、遺言の内容を法的な観点からチェックしてくれるので、ご自身だけで作成する自筆証書遺言に比べて、作成ミスが起きにくいといったメリットがあります。
また、公証人は遺言作成手続きが適正に行われたかどうかについても証明してくれるので、相続開始後に、遺言者の判断能力が争われたときにも、遺言の有効性を主張しやすくなると言えるでしょう。
自宅で保管しなくて良いので紛失のリスクがない
公正証書遺言の場合、遺言の保管は公証役場において行われます。
ご自身での保管が必要な自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて、紛失の心配がないという点が大きなメリットです。
デメリットと注意点
公正証書遺言を選択した場合、公証人に支払う手数料が必要となってくるため、気軽に作成できる自筆証書遺言に比べると、作成費用がかかるといった側面があります。
また、戸籍や住民票、不動産評価額が分かる資料など、公証役場に提出する書類が多岐に渡る場合もあり、必要書類を収集する負担が生じる場合も。
自筆証書遺言に比べると事務手続きが多くて尻込みしてしまうかもしれませんが、遺言の真正が担保されるメリットを思うと、少し手間がかかったとしても、公正証書遺言を選択する価値はあるのではないでしょうか。
秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしておきながら認証を受けられる
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく作成することのできる方式です。
作成は、遺言者が作成した遺言を封筒に入れた上で、遺言に押印した印鑑と同じ印鑑で封印をすることによって行います。
この遺言の入った封筒を、公証役場に持ち込んで認証を受けることで、間違いなく遺言者が書いた遺言だということが証明されるのです。
封筒は相続開始まで開けられることがないため、周囲に遺言の内容を秘密にしておくことができ、遺言の偽造防止などに効果があります。
自筆する必要がない
秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言のように全文が自筆であることは求められていないため、PCで作成したものであっても有効です。
遺言書を全て手書きで書くという作業は手間のかかる大変なことなので、自筆でなくても良いという点は大きなメリットだと言えます。
方式の不備があると無効になることも
公証人の認証を受ける点では、公正証書遺言と似ているように思いますが、秘密証書遺言の場合、遺言の封筒は相続開始まで開かれることがないため、公証人に遺言の形式や内容の不備がないかを確認してもらうことはできません。
遺言に不備があった場合に無効となるリスクは、秘密証書遺言では避けられないということを、理解しておく必要があるでしょう。
遺言の作成に迷ったときは行政書士にご相談ください

今回は、遺言における3つの方式と各特徴についてご説明しました。
それぞれの方式にはメリットもあれば、デメリットや注意しなければならないこともいくつかあります。
ご自身が希望する遺産相続を円滑に進めるためにも、どの方式を選択するかは慎重に判断しなければなりません。
遺言の方式の選択や遺言書の作成に悩まれた場合は、相続の専門家である行政書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きが進められることと思います。
当事務所はこれまでに、上田市をはじめとする長野県全域において、様々なケースにおける遺言作成に対応してまいりました。
相談や書類作成のサポートのみの場合は全国対応しますので、お困りの際は当事務所へお気軽にご相談ください。
まとめ

いかがだったでしょうか。
遺言の作成は難しそうだと感じられている方も少なくないと思いますが、元気なうちに遺言を用意しておくことで、ご家族の相続手続きを円満に進めていくことができます。
今回の記事をきっかけに、遺言の作成に関心を持たれる方が少しでも多くいらっしゃると幸いです。
