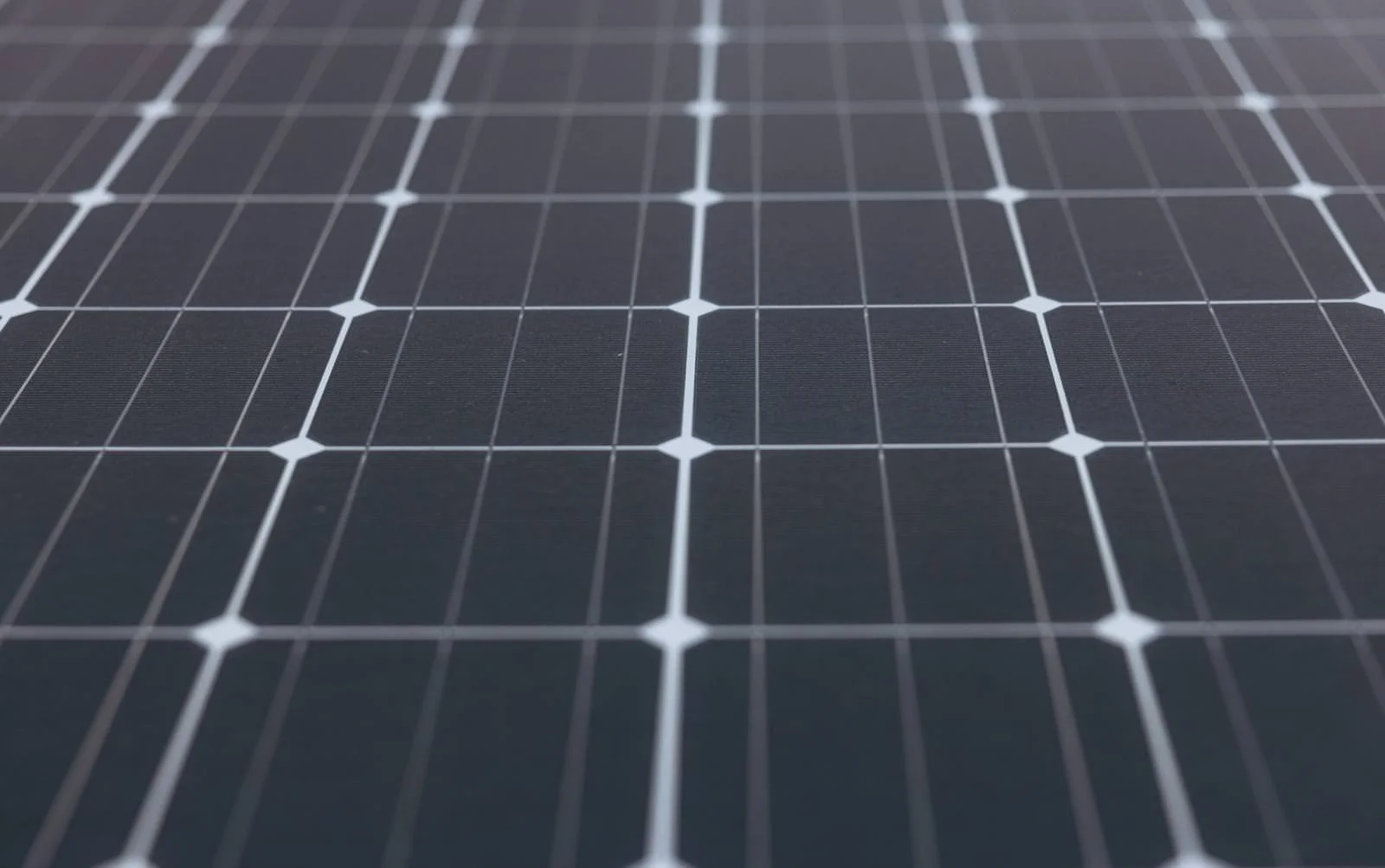
「耕作していない農地にソーラーパネルを立てたいけど、何から始めればいい?」
「うちの土地は転用できなさそうだから、太陽光発電はできないかな…」
「農業をしながらソーラーパネルを設置できないだろうか?」
昨今、農地を有効活用して太陽光発電を始めてみたいという方からのご相談が増えています。現在更地だからといって、農地転用の手続きをとらずに始めてしまっては、罰則を受けたり、トラブルが起きたりする原因になりかねません。
本記事では、農地転用を伴う太陽光パネルの設置について、農地転用の専門知識を持つ行政書士が、手続きのポイントをご説明します。
当事務所では、上田市をはじめとして長野県全域において、建設業許可申請、農地転用、遺言相続、会社設立などの各種手続に関し、書類の作成代行や作成代理および官公署への提出代理などを幅広く行っていますので、お気軽にご相談・ご依頼ください。
手続きの流れ

手続きの全体像
農地に太陽光パネルを設置するにあたっては、現況が更地だからといって、無断で好きなように設置をして良いわけではありません。
農地の適正な利用という観点から、農地転用の手続きをとる必要があります。
手続き先は、各自治体に設置されている農業委員会です。
手続きの大まかな流れは以下のとおりで、行政書士にご相談いただいた場合、①の段階から申請書の提出をトータルでサポートすることが可能です。
①転用可能性の調査
②必要書類の用意
③申請書の作成・提出
①転用可能性の調査
まず何よりも先立つことは、ご自身の所有する農地が、農地転用可能な農地なのかどうかを確認することです。
農地の種類によっては転用不可の場合があるため、計画をスムーズに進めていくためにも、転用ができるかどうかは一番に確認するようにしましょう。
【転用できる農地】
| 第二種農地 | いずれ市街化する可能性のある農地 |
| 第三種農地 | 市街地の中にある農地 |
【転用できない農地】(※場合によって転用可能となることがあります。)
| 農用地区域内農地 | 農業振興を図る農業振興地域として、都道府県知事によって指定された地域内にある農地 |
| 甲種農地 | 集団的に存在する生産性の高い優良農地 |
| 第一種農地 | 10ヘクタール以上の集団農地 |
なお、農地の種類については、農業委員会事務局の窓口において確認が可能ですが、現地調査が必要な場合など、すぐに確認がとれないようなケースもあるので、スケジュールに余裕をもって動き始めましょう。
また、転用可能な第二種農地、第三種農地の場合でも、周囲の農地との関係で転用不可とされる場合もあるので、一概には言えません。
自己判断ではなく、まずは農業委員会の窓口で確認をすることが重要です。
②必要書類の用意
農地の種類の確認ができたら、次は申請に必要な書類を用意していきましょう。
主な必要書類としては、許可申請書、土地の登記事項証明書、農地の図面や現況写真、事業計画書など揃える書類は多岐に渡り、また転用する農地の種類によっても、必要とされる書類が変わってきます。
ご自身のケースに応じた必要書類の判断が難しい、不安だという場合は行政書士にご相談いただければ全面的にサポートいたします。
③申請書の作成・提出
申請書と必要な添付書類の用意が整ったら、各自治体の農業委員会へ申請に行きます。
ただし自治体によっては、地区ごとの農業委員の方に書類を確認してもらい、署名押印をもらうという段階を踏まなければならない場合もあります。
注意すべき点として、農地転用の許可申請には、月1回の締め切り日が設けられています。
この締切日を意識して準備をしていかないと、予定していた日までに許可がおりないということも考えられるので、余裕を持って申請に臨むようにしましょう。
転用できない土地だから諦めないといけない?

転用可能にしていく方法はあります
農業委員会で確認すると、所有している農地は第一種農地などの転用できない農地だった場合。
「農地に太陽光パネルを設置するのは諦めないとだな…。」
そんなことはありません。
転用できない農地でも、場合によっては転用できる可能性があります。
甲種又は第一種農地の場合
甲種又は第一種農地の場合でも、「農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの」(農地法施工令第11条第1項第1号ロ)である場合は、転用が認められる可能性があります。
ご自身が検討する太陽光パネル設置計画が、現在の農地にどの程度影響を及ぼすかは農業委員会窓口との相談が必要です。
農用地区域内農地の場合
農用地区域内農地は、農地の種類の中で最も転用のハードルが高そうですが、転用が全くできないわけではありません。
農地転用に先立って、「農業振興地域整備計画の変更に伴う協議(農振除外申請)」を行うことで、通常の農地転用をすることが可能となってきます。
ただし、農振除外申請の受付期間は毎年一定の期間しか設けられておらず、審査にも半年から1年程度かかるとされています。
すぐに決定がおりるわけではないので、申請のタイミングを逃さないよう注意しておく必要があります。
農業をしながら太陽光発電を取り入れることも可能です

ソーラーシェアリングで収益アップ
農業をされている方が、農地の空いている上部空間を活用して、太陽光パネルを設置することも可能です。
これは「ソーラーシェアリング」と呼ばれる手法で、農業にプラスして発電事業も行え、収益アップに繋げることができるというメリットがあります。
またSDGsの観点からも、農作物の光合成によるCO2吸収、太陽光発電によるエコな発電という両面で環境保全に貢献することも可能であり、近年注目されている分野でもあります。
一時転用の手続きが必要
農業を継続しながら太陽光パネルを設置するには、「営農継続型一時転用」の手続きが必要です。
許可を受けるためには、農作物の収穫量や品質に影響を及ぼさないことや、農地の専有部分は太陽光パネルの支柱部分に限るなどの条件を満たしている必要があります。
あくまでも農業を継続することが前提となるので、毎年農作物の収穫量を報告する必要がある点に注意が必要です。
一時転用許可には有効期限があります
一時転用許可には、3年に一度更新が必要です。
継続して営農継続型一時転用の許可を受ける場合は、更新手続きを忘れないようにしましょう。
更新手続きの際には、農業が継続して行われているか、農作物の収穫量が大幅に減少していないかなどのチェックを受ける必要があります。
行政書士は農地転用に関する疑問を解消いたします

農地に太陽光パネルを設置するためには、農地転用の手続きが必要だということをお伝えさせていただきました。
申請にあたっては、ケースに応じた様々な書類を揃える必要があるなど、ご自身の判断だけでは難しい部分もあるかと思います。
そのような場合は、農地転用のプロフェッショナルである行政書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることが可能となるでしょう。
当事務所はこれまでに、上田市をはじめとする長野県全域において、農地転用の様々な事例に対応してまいりました。
農地転用手続きに関してお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ

耕作していない農地に太陽光パネルを設置することで、利用していない農地を有効に活用することができます。
相続などで農地を承継し、利用方法に困っているという方は、太陽光パネルの設置も視野に入れてみてはどうでしょうか。
