
「相続人の相続権はいかなる場合も認められる?」
「推定相続人の中に相続をさせたくない人がいる」
「遺言によって相続をさせない意思表示はできるのか」
相続が開始すると、一般的には亡くなった方の配偶者や子が推定相続人となりますが、なかには事情があって、特定の推定相続人に遺産を渡したくないという場合もあるかと思います。
少し過激なお話になってしまいますが、例えば、早く遺産を相続したいがために、被相続人を故意に死に至らしめようとした場合や、また、日常的に虐待を行っていたという場合、危害を加えた者に相続権を認めることには疑問が生じてくるでしょう。
そこで、民法には相続権を認めがたいケースに対処できるよう、「相続欠格」「相続人の廃除」の規定が設けられています。
当記事では、相続欠格や相続人の廃除の具体的な内容について、これまで多くの相続手続きを手がけてきた行政書士が詳しくご説明したいと思います。
当事務所では、上田市をはじめとして長野県全域において、建設業許可申請、農地転用、遺言相続、会社設立などの各種手続に関し、書類の作成代行や作成代理および官公署への提出代理などを幅広く行っています。
ご相談や書類作成のみの場合は全国対応もしますのでお気軽にご連絡ください。
相続欠格とはどのようなものか?

法律上当然に相続権を失う
相続欠格者に該当するかどうかは、裁判所の判決によって決まるものではありません。
次に掲げる5つの欠格事由にあてはまった場合、特段の手続きを要せずとも、相続人の資格は剥奪されます。
相続制度の基礎にあるのは、被相続人を中心とした、配偶者、子、父母、兄弟姉妹といった家族的共同生活です。
その根管を揺るがすような行為をした者に、相続権を認めることは妥当でないという考えのもと、このような厳しい規定が設けられていると言えます。
相続欠格に該当する5つのケース
相続欠格者とされるのは、次の5つの場合(民法891条)です。
①故意に被相続人または先順位者や同順位にある相続人を死亡させ、もしくは死亡させようとしたために刑に処せられた場合
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合
③詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をしたり、その撤回・取消し・変更をしようとしたりするのを妨げた場合
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回・取消し・変更をさせたりした場合
⑤遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した場合
相続欠格に該当するとどうなるか?
相続欠格事由に該当した場合、相続人としての地位は当然に失われるため、改めて裁判所に申し立てをする必要はありません。
また、欠格事由が相続開始後に発覚した場合、相続欠格の効力は相続開始時に遡って適用されます。
ゆえに、欠格事由のある者が既に相続を済ませてしまった場合でも、他の相続人はこの者に対して、相続回復の請求をすることができるのです。
ここで注意したいのが、相続欠格の効果は、被相続人と該当者の間でのみ発生するという点です。
例えば、父親との関係では相続欠格に該当したとしても、母親の相続については相続権は失われません。
また、相続欠格の効果はその本人に限られるため、相続欠格者に子がいる場合は、その子が代襲相続をすることは可能となります。
相続人の廃除とはどのようなものか?

被相続人の意思で相続権を剥奪
法定相続人の相続権を剥奪する方法としては、「相続人の廃除」という制度も設けられています。
これは、被相続人に対して虐待や侮辱、著しい非行をした者を、被相続人の意思で相続人から廃除するものです。
被相続人から家庭裁判所への申し出をする必要がある点が、相続欠格との大きな違いとなります。
家庭裁判所の審判を経て、廃除の決定を受けたときに、はじめて相続人としての地位が剥奪されるのです。
相続人の廃除を受けるとどうなるか
相続廃除の審判が確定した場合、申立人は審判確定日から10日以内に、市区町村役場の戸籍課へ届出をする必要があります。
これは、推定相続人の戸籍に、推定相続人廃除の記載がされるためです。
相続欠格の場合は、法律上当然に欠格となるため、戸籍にまでその旨が記載されることはないのですが、廃除の場合はひと目で廃除されていることが分かるように、戸籍中に廃除の旨が記載されるようになっています。
また、相続人の廃除の場合も相続欠格と同様に、代襲相続は可能です。
廃除の決定は後から取り消すことも可能
相続欠格は基本的に取り消すことはできませんが、相続人の廃除の場合は、状況の変化に応じて取消しが可能となっています。
例えば、廃除の申し立てをした後に、推定相続人が心を改めてくれて、被相続人との関係性が良くなることもあるでしょう。
そのような場合には、再度家庭裁判所に請求することによって、廃除の取消しをしてもらうといった道もあるのです。
廃除の申し立ては遺言でも可能
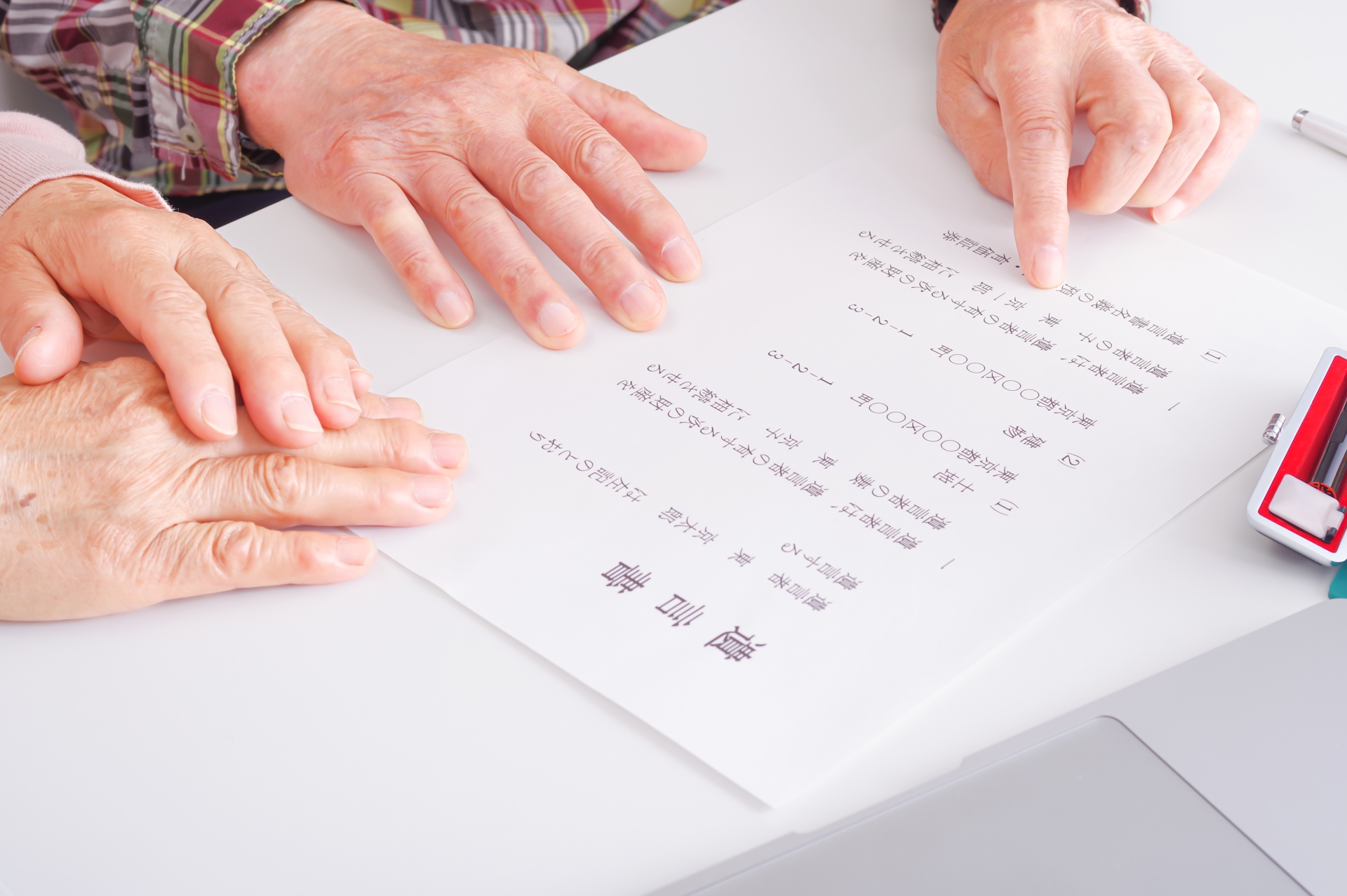
生前に廃除の申し立てをするのは気が引ける…
相続人廃除の制度があるおかげで、被相続人の意思を尊重することはできますが、場合によっては、廃除の申し立てをすることによって、推定相続人との関係性が悪化してしまうおそれもあります。
申し立てをしたばかりに、相手を逆上させてしまって、余計に暴力や暴言を振るわれることになってしまうようなことは、出来る限り避けたいところです。
こういった懸念がある場合、生前に廃除を申し立てるのではなく、遺言に思いを託すという方法を検討するのが良いかもしれません。
遺言で廃除の意思を示す場合の文例
実際に遺言に廃除の意思表示をする場合、遺言には以下のような内容を記載すると良いでしょう。
「遺言者の長男A(昭和X年X月X日生まれ)は、遺言者に、日常的に殴る蹴るなどの暴行を加え、令和X年X月X日には、遺言者に全治3カ月を要する傷害を負わせるなどの行為をしたので、遺言者は、長男Aを推定相続人から廃除する。」
こちらはほんの一例になりますが、このような感じで、その者を廃除したい具体的な理由を、遺言の中で明らかにする必要があります。
廃除が認められない場合があることに注意
廃除の申し立てに対する決定は、家庭裁判所の慎重な判断のもとに行われることになります。
決定に際しては、申立人の意見だけでなく、相手方の意見も聞き取った上で公平な判断をしていくことになるのです。
よって、遺言で廃除の申し立てをした場合、将来、実際に廃除が認められるのかどうかは、被相続人本人には分からないこととなります。
不安がある場合は、生前に廃除の申し立てをしておいた方が良いのかもしれませんが、様々な事情により難しい場合は、遺言執行者を指定し、廃除の意思を伝えておくといった工夫が必要かと思われます。
相続に関する疑問なら行政書士にお任せください

今回は、相続欠格や相続人の廃除の概要、それらによって発生する相続への影響などについてご説明しました。
法的な専門知識が必要とされる相続手続きに関して、まだまだご不明な点もあるかと思います。
そんなときは、相続手続きの専門家である行政書士に、ぜひご相談ください。
当事務所はこれまでに、上田市をはじめとする長野県全域において、遺言書作成や遺産分割などの各種相続手続きに対応してまいりました。
相談や書類作成のサポートのみの場合は全国対応しますので、お困りの際は当事務所へお気軽にご相談ください。
まとめ

遺産相続は、人生においてそう何度も経験することではありません。
そのため、初めての手続きでどうすれば良いか分からないという方も、多くいらっしゃるかと思います。
相続手続きを円滑に進めていくことをサポートするのが、私たち行政書士の役目です。
相続に関する疑問やご不明なことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
